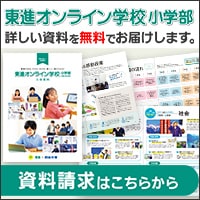- 大学付属校って、中高一貫進学校と何が違うの?
- 大学付属校に合格するための勉強法は?
そんなお悩みにお答えします!
我が家では、2人の息子が中学受験をして「大学付属校」と「中高一貫進学校」に進学しています。
本記事では、それらの経験をもとに「大学付属校と中高一貫進学校の違い」と「大学付属校に合格するための勉強法」についてお答えします。
大学付属校への受験を考えている方は、参考にしてください。
中学受験で受験できる「大学付属校」の紹介
現在、中学受験で大学付属校を目指す受験生が増えています。
このように考える親は多いと思います。(僕もそうです)
しかし、現在は早慶GMARCHを中心とする大学付属校は人気が非常に高くどの学校も難関校となっています。
子どもの偏差値との差を見てため息をつき、合格判定率を見て諦めたくなる人もいるかもしれません。参考に、早慶MARCHの付属校の偏差値を紹介します。(一部の学校のみ)
| 学校名 | 偏差値 |
|---|---|
| 慶應義塾中等部 | 男75 女77 |
| 早稲田大学高等学院中等部 | 男72 |
| 明治大学付属明治中学校 | 男71 女73 |
| 青山学院中等部 | 男69 女72 |
| 立教池袋中学校 | 男67 |
| 中央大学付属中学校 | 男66 女67 |
| 法政大学中学校 | 男65 女67 |
参照元:首都圏模試センター「2021年中学入試予想偏差値(合格率80%)」
我が家の大学付属校の中学受験経験
この記事を書いている僕は、中学受験経験者で大学付属校の出身です。
息子も中学受験を経て大学付属校へ進学しています。
小6春時点の偏差値は、第1志望校に全く届かず、志望校判定は20%。
そんな状態から、大学付属校に焦点をあてた勉強法に取り組んで、偏差値を12上げて第1志望の大学付属校に逆転合格しました。
詳しくは、【中学受験】家庭教師を利用して偏差値12アップした合格体験談という記事に書いています。
また、受験した学校や入試当日の様子については、中学受験体験記として記録していますので、よかったら合わせてご覧になって下さい。
中学受験で大学付属校に合格するための勉強法
続いて、中学受験で大学付属校に合格するための勉強法を8つ紹介します。
その1:中学受験の目的を明確にする
中学受験で大学付属校を目指す理由の1つとして「大学受験をしなくて済む」という理由があると思います。
この目標を、もう少し深堀りしたいと思います。
- 具体的にお子さんが6年間取り組みたいと考えている好きな事は何でしょうか?
- お子さんは、本当に大学受験の事を理解できていますか?
- 単に、合格したらそのあと勉強しなくていいよ。と言っていませんか?
- 中学受験の目的は親子で一致していますか?
中学受験は長丁場です、目的が明確でないと辛いときに踏ん張ることができなくなってしまいます。
また、慶應義塾中等部や慶應義塾湘南藤沢中等部では親子面接があります。そこで、親子で共通の思いを持っていないと、面接が上手くいかない可能性が高いです。
目的に関しては、どんなささいなものでも良いと思います。
息子の場合は「もみあげを切りたくないから中学受験したい」でした。
「えっ、そんなことで?」と思われると思います。僕も思いました。(笑)
どんなに子どもっぽい目的だったとして、子ども自身が考えた目的であれば、子どもにとって大きなモチベーションになります。
ちなみに、入学以来ずっと伸ばしていたもみあげですが、最近は心境の変化があったのか、切ろうか悩んでいる様子です。(笑)
その2:入試問題でだされる問題の特徴をおさえる
大学付属校と進学校では、入試でだされる問題の特徴が全く違います。
もちろん、大学付属校の中でも違いはありますが、大まかにいうと次のようになります。
付属校は、基本問題の出題。難易度はやさしめ
進学校は、応用問題の出題。難易度は難しめ
また、基本問題に加えて生活の知識やマナーに関する問題がでてくることが多いです。
最近、話題になっている慶應普通部の「もやしの値段を問う問題」も、生活関連の問題です。
こういった問題は塾のテキストだけやっていても解くことはできないので、過去問で特徴を抑えたうえで、日々の生活の中で親が声かけをしていく必要があります。
慶應では過去にテーブルマナーに関する問題が出されたこともあったので、対策としてきちんとしたレストランで食事をして、食器を使う順番など、基本的なマナーを教えたりもしました。
その3:繰り返し過去問を解いて問題の特徴を体で覚える
大学付属校と進学校の大きな違いとして、入試問題の特徴が大きく変わらないということもあげられます。
付属校は、毎年問題の傾向が大きく変わらない
進学校は、毎年ひねった問題を出してきたり、大きく問題を変えてきたりという事がある
付属校には学校が求める確固たる生徒像があります。
それは、大学の入試制度が変わろうが大きく変わる事はないです。
求める生徒像が変わらないから、入試問題にも大きな変更がありません。
入試問題が毎年大きく変わらないのであれば、過去問を繰り返し解いて対策に時間をかけている子どもの方が圧倒的に有利です。
我が家でも第1志望校の過去問は10年分を繰り返し解いていました。特に、理科と社会に関しては何度も解き直しをして、まさに問題の特徴を体に覚えさせていました。
その4:子どものやる気をオンにする
子どもは、親の期待に応えたいという気持ちを持っています。
だから、「親が勉強やりなさい」と言えば、たとえ嫌だと思っていてもやります。(やらない事もありますが)
もちろん嫌々勉強しても効率はあがりません。そのもう一歩先、親の期待が本当の意味で理解できるようになると、親へ感謝する気持ちが生まれ「やる気」がオンになる事があります。
親が子どもに直接「感謝しろ」という話はできないし逆効果になる事が多いと思うので、第三者からそれとなく伝えてもらっても良いと思います。
すでに中学受験が終わっている長男に、親への感謝の気持ちがいつ芽生えたか聞いてみました。
子どもの「やるき気」をオンにする方法については、中学受験生が自分から勉強したくなる!やる気スイッチを見つける方法という記事でも書いています。
その5:子どもに説明してもらう
アメリカ国立訓練研究所の発表している平均学習定着率(ラーニングピラミッド)による、人は講義を受けたり、本を読むだけでは15%程度しか学習内容が定着しないそうです。
一方で、人に教えたり・説明すると90%の定着率となる事がわかっています。
要は、インプットよりアウトプットをした方が学習内容が定着するという事です。
そのため塾で授業を受けた後に、塾で習った内容を子どもが説明をする事で学習の定着率は格段に上がります。
我が家でも子どもが塾から帰ってきた後に、色々と授業の内容を質問しています。
(子どもの学年が上がってくると、面倒くさがって段々と話してくれなくなりましたが。。)
子どもが授業の内容を話してくれない時は、事前に伝えておく方が良いようです。
お子さんが塾へ行く前に、「今日塾で習ったことを帰ったママ(パパ)に教えてね」と伝えておきます。そして帰ってきたら、塾での勉強の内容を子どもに解説してもらうのです。
旅行ですが、「印象に残ったことを三つ、帰ったら聞かせてね」と伝えておくと、お子さんは印象に残るものを見つけようと一生懸命になり、お土産話が盛りだくさんになるものです。
参照元:野田英夫著「中学受験大学付属校合格バイブル」
知識を定着化させる効果的な勉強法については、中学受験で偏差値がアップする勉強法!漢字の書き取り、蛍光ペンでマークはダメという記事でオススメ書籍と一緒に、より詳しく触れています。
その6:子どもに問いかけをする
子どもに説明してもらうことと似てますが、親がちょっとした問いかけを子どもにしてあげる事で、子どもの成績の伸びは大きく変わってきます。
一緒にニュース番組を見ていたら、「どう思う?」「〇〇くん、だったらどうする?」と子どもの意見を聞いたり、解決策を考えさせたりする質問を積極的に投げかけます。
質問されることで子どもが考えるようになりますし、日常的に問いかけをしていると、今度は子ども自身が自分に対して問いかけをして、思考出来るようになります。
例え子どもの考えが見当違いな意見だったとしても、子どもの意見や考えを否定して「正解」を言ってしまわないようにすること。
せっかくの意見が否定されたら、答える気がなくなってしまいます。
中学受験における親の役割は、勉強を教えてくれることではなく、日常生活の中で子どもに質問し、子どもに教えてもらうことです。
ちなみに、子どもと一緒にテレビをみるときは「ブラタモリ」のように、面白くて知識も増える番組がおすすめです。
小学生が社会を好きになるおすすめ番組5選!という記事で、おすすめ番組を紹介しています。
その7:模試の解き直しをする
模試を受けた際に、大切なことは2つ。
- 正答率をみること
- 解き直しをすること
決して、偏差値を見て一喜一憂するだけで終わってはいけません。(僕もやりがちなので反省です)
必ず、各問題の「正答率」を見て、解き直しをする必要があります。
正答率70%以上の問題
基本問題です。必ず出来るようになるまで解き直しをする必要があります。
正答率が20%以下の問題
いわゆる難しい問題です。付属校狙いであれば必ずしも出来る必要はないですし、もし子どもが出来ていたら得意分野という事になります。
また、どの分野の問題を間違ったのかを見る必要があります。
苦手分野を把握して、次の模試や別の模試でその苦手分野ができていたら、すかさず褒めましょう。
これが結構大変で、僕も全然できていません。それなりに間違えている量が多かったりすると、子どもの苦手分野の把握が追い付きません。
我が家では、算数と理科に関しては家庭教師を週1回つけているので、算数と理科に関しての苦手分野の把握は家庭教師にお願いしています。
親が全てをやることも難しいので、任せられるところは任せた方が楽です。
家庭教師の効果的な使い方については、【中学受験】家庭教師を利用して偏差値12アップした合格体験談でも紹介しています。
その8:家庭だけで対策が難しい人は家庭教師を頼む
付属校対策には、過去問を何回も解いて問題の特徴を覚える。そのためにも、何回も解き直しを行う。という事をお伝えしましたが、子どもだけで取り組むのはなかなか難しいです。
というのも、ほとんどの子は一度解いた問題の解き直しをするのが嫌いだからです。
自分が解けなかった問題は見たくないし、苦手だから勉強したくないのです。
基本的に過去問の解き直しをするのは自習の時間になります。自立していて自分で解き直しをできる子はいいですが、そうでない子は親がコントロールしてあげないといけません。
親が子どもの解答を確認して苦手な分野を見極め、過去の教科書を参照させたり、ノートの見返しをさせる必要がありますが、そこまで時間を取れない家庭も多いと思います。(我が家もそうです)
そういう場合は、家庭教師をつけてみるのもオススメです。
我が家の家庭教師体験談は、コチラの記事で書いています。
Sと並行して家庭教師をオンラインで週1回1時間お願いしているけど、組み分けテストのように単元広いときはホント助かる?子どもの苦手な単元を把握してるから、子どもの苦手な単元の問題をバッとその場で復習してくれる。
親の方で1つ1つ苦手単元を整理して、問題準備してというのは大変なので?— しろくま@中受2022年組 (@shirokumanabu) June 28, 2020
進学してわかった「大学付属校」と「中高一貫進学校」の違い
我が家は、長男が「大学付属校」、次男が「中高一貫進学校」に進学しています。実際に進学してわかった、それぞれの違いについて紹介します。あくまで、我が家で進学した学校をベースにした体験談なので、学校によって違いはあると思います。
学習面の違い
授業内容:先生の入れ替わりがなく、受験もないのでマンネリ化しがち。
スピード:公立中より多少速いくらい。
宿題の量:締切の前日に頑張れば何とかなる。
学習時間:ほぼ0分。小テストや試験前のみ学習。
モチベーション:毎日1時間勉強していたら優秀層。
授業内容:先生も指導力の向上を日々求められており、面白い授業が多い。
スピード:中3から高校の内容に入る。非常に速い。
宿題の量:特に数学の量が多い。毎日の学習が必須。
学習時間:1−2時間程度。
モチベーション:春休みにどれだけ勉強したかを競っている。
進学・留年の違い
- 一定ラインの成績を下回ると中学校でも留年する
- 実際に、毎年全体で1人、2人は留年することも
- 高校では、毎年必ずクラスで1人、2人は留年している
- 学部毎に推薦枠が決まっているので、希望の学部に進学できるかは成績次第
- 基本的に中学生での留年はない。
- 基準点に達していない場合は、審議の対象となる。
学費の違い
大学付属校と中高一貫進学校の「入学金」「授業料(3年間)」「その他費用(3年間)」「寄付金」について、紹介します。もちろん学校によって異なるので、ご参考程度に。
| 学校 | 入学金 | 授業料 | その他※1 | 寄付金 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大学付属校 | 34万円 | 256万円 | 40万円 | ※2 | 330万円 |
| 中高一貫進学校 | 25万円 | 150万円 | 180万円 | 30万円 | 385万円 |
※1:その他には、制服代、修学旅行費、指定の物品費を含みます
※2:学校によりますが、長男の通った学校は強制ではありませんでした。もちろん、中高一貫進学校でも強制でない学校もあります。
通塾生の割合の違い
- 体感で全体の2割くらいが通塾。
- J PREPなど英語系の塾が人気。
- 留年する可能性がある子は、家庭教師をつけることも。
- 中学校では全体の5割くらい。
- 高校になると、8割を超える学校も。
自由度の違い
- 自由と言っているが、新しい部活を創ることができない
- 自主性を謳っているが、文化祭や運動会の運営は先生が主体
- 昔からある謎な校則が、今も残っていたりする
- 生徒が臨めば、新しい部活を創ることができる
- 文化祭や運動会の運営は生徒が主体
- 制服の着用ルールが厳しい
雰囲気の違い
- 素直でおっとりした子が多い印象。
- 付属小学校出身はスーパーなお金持ちがチラホラいる。
- 中学校からの入学者はサラリーマン家庭も多い。
- 付属小学校から上がってきた保護者は固まりがち。
- 保護者会に参加する母親は全員紺スーツ。
- 成績にこだわる子が多いわけでもなく、勉強する人もいれば勉強しない人もいる
- 暗い人もいれば、明るい人もいるが、その間での対立はない。
- 親の雰囲気はバラバラ。服装も割と緩い。
子どもの様子の違い
毎日勉強に追われている感じがなく、毎日部活と友達との遊びで充実してそう。一方で、長期の休みや、部活引退後は暇を持て余していました。
大学の意向に従う必要があるため、コロナ渦において学校行事が大きく減らされたのが不満です。
毎日机に向かう時間を確保していないと、落ちこぼれていきそうな感じがする。ただ、中学生のうちは、そんなに大学受験を意識することもないようで、休日は友達とオンラインゲームで遊ぶことも。
まとめ:中学受験における大学付属校と進学校の違いについて
全体的に大学付属校の評価が低めだと感じるかも知れませんが、大学付属校に進学することのメリットは「大学受験をしなくてよいこと」に尽きます。
時間に余裕のある学生生活が送れるので、勉強以外の部活や習い事に打ち込みたい子にとっては最適な環境です。
また、親にとっても受験のストレスから解放されるので、心理的負担もありません。
金銭面で考えても、大学受験に備えた塾代を考えると大学付属校の方が安く収まるケースが多いです。
大学付属校によっては、中学と高校で雰囲気が結構違う学校もあります。また、付属校も学校によっては大学への推薦枠に違いがあるので、よく調べておきましょう。
さいごに1つだけ、自宅で出来るライバルの一歩先をいく中学受験準備情報をお伝えします。
中学受験が本格的に始まるのは小学4年生(小学3年生の2月)からですが、入塾時点で上のクラスを目指すためには低学年からの準備が欠かせません。
そうはいっても、習い事もやっているし毎週塾に行くのは大変という方も多いのではないでしょうか。
そんなご家庭に朗報です!
中学受験大手”四谷大塚”の名物講師の授業が「自宅で受けられるオンライン塾」があるんです!
東進オンライン学校小学部では、四谷大塚の教材を使った授業を自宅で受けられます。
しかも料金は月々たったの1,980円(税込2,178円)※小3以降は2,980円(税込3,278円)
ちなみに、四谷大塚の小学1年生クラスは13,200円なので圧倒的にお得です!
- 低学年のうちから中学受験準備をしたい
- 通塾は大変なので、自宅で学習したい
- なるべく塾にかかる費用は抑えたい
さらに、10日間はお試し入会できるのでお子さんに合わなかったら即解約すれば全額返金されます。
まずは資料請求(無料)をして、詳細を確認しましょう!
\10日間おためし無料/
画面下の資料請求ボタンから申し込み
ちなみに、大半のお子さんは入塾時のクラスと小6のクラスは、あまり変わらないので入塾前の準備が重要です。(体験談)

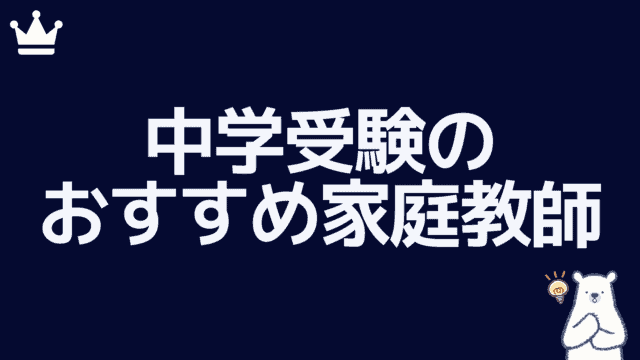
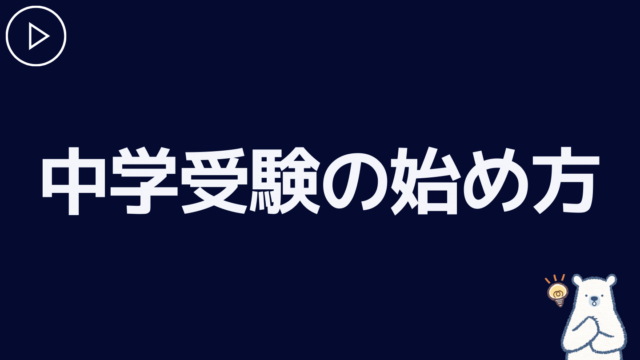
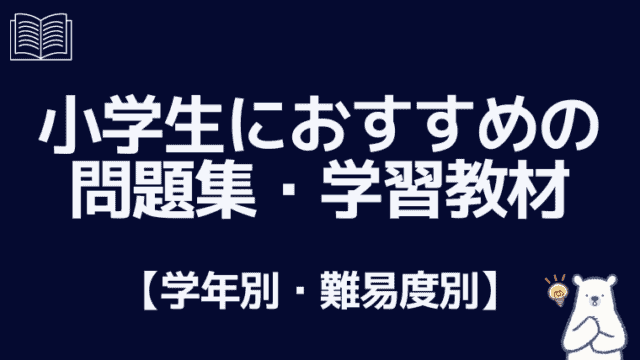
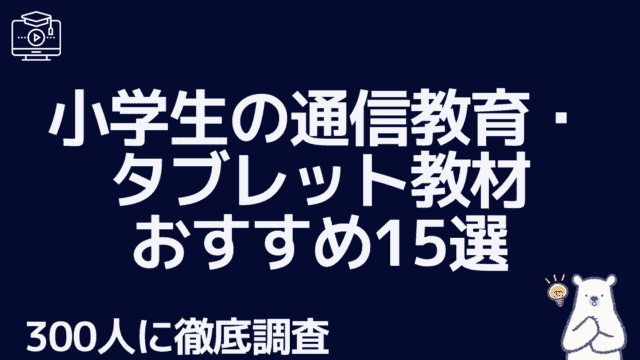
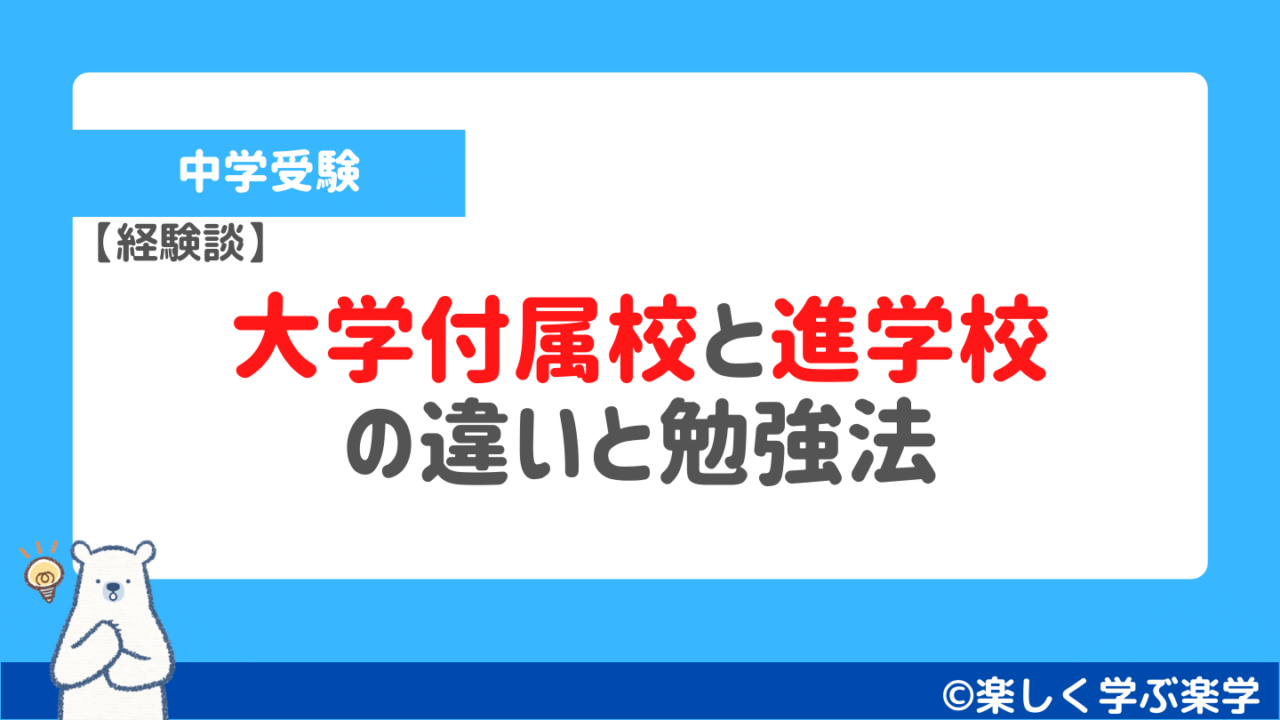






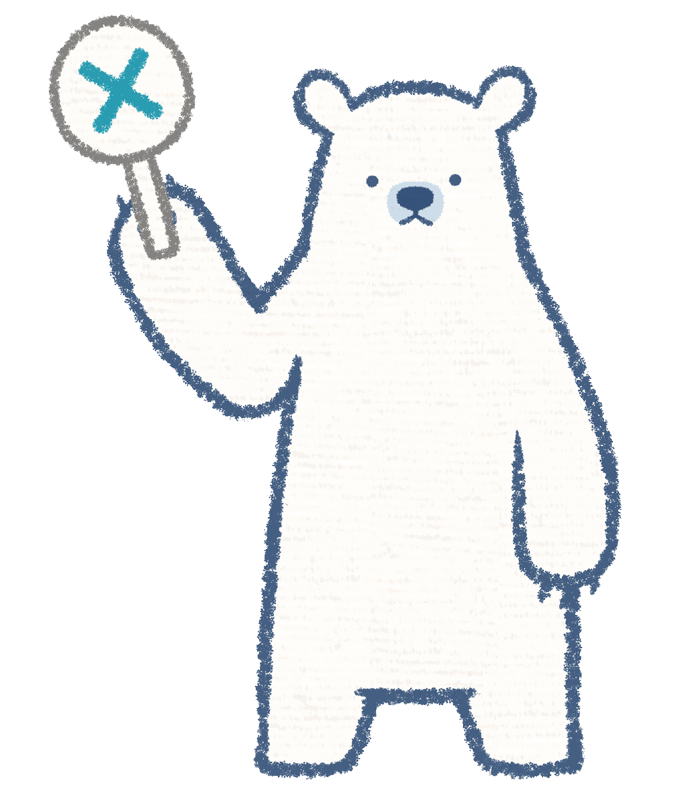




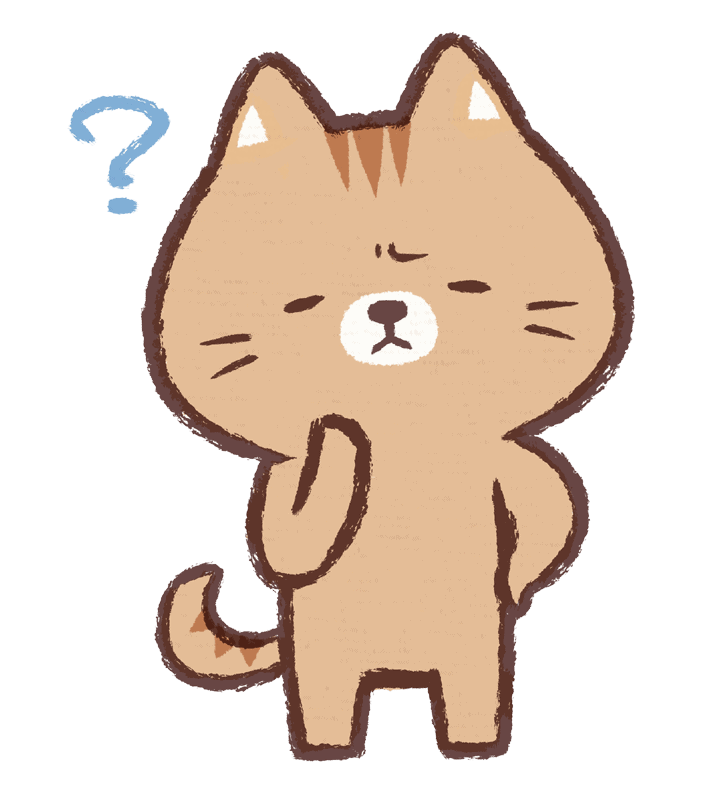

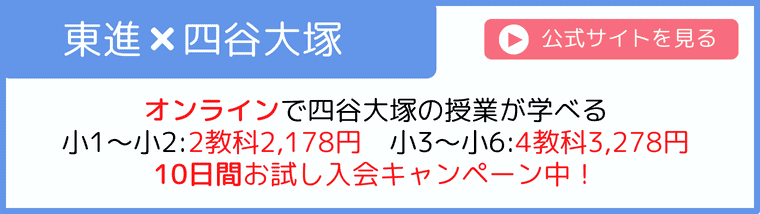
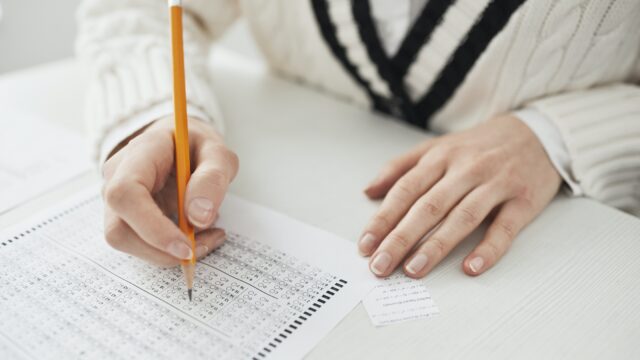
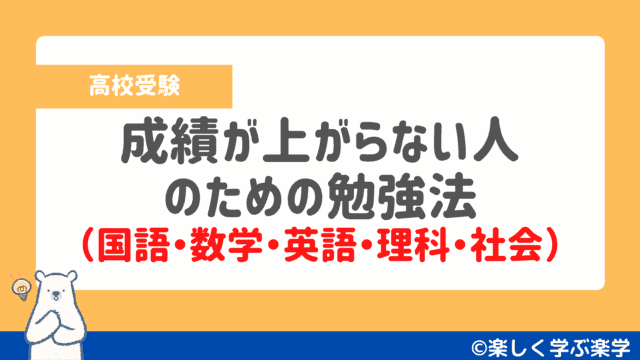
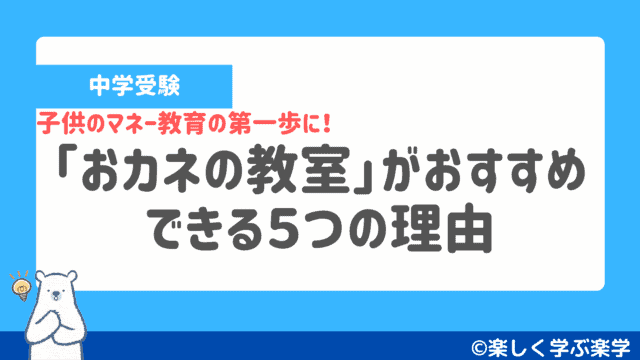

 個別指導SS-1
個別指導SS-1 
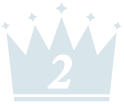 個別教室のトライ
個別教室のトライ 
 国語特化の個別指導ヨミサマ。
国語特化の個別指導ヨミサマ。