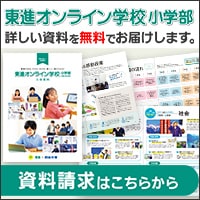回答を確認したい質問の目次をクリックしてご覧ください!
大手塾の入塾テスト対策はどんなことをしたらいいでしょうか?
大手塾の入塾テスト、初めてだと不安ですよね。
過去問や公開されているサンプル問題を解いて、出題傾向を知るのが大切です✍️特に国語は読解慣れ、算数は計算力と文章題に触れておくと安心です。
家庭でミニテスト形式にして練習するのもおすすめですよ
希望の大学学部を決めるきっかけ、タイミングがわかりません
進路選びは迷って当然。でも、少しずつヒントは見つかります😊
① 興味のあることを書き出そう
- 得意・好きなことを整理
- 好きな教科や趣味、将来なりたい姿から逆算
② 大学の学部パンフやオープンキャンパスを活用
- 実際に「見て・知る」体験を
- 雰囲気や内容でピンとくることも
③ タイミングは「気になった今」
今わからなくてもOK、探し始めがベストタイミング!
🐻❄️しろくまのひとこと
正解はひとつじゃないし、進路は後から変えてもいい。無理せず、笑顔で進んでいきましょう!
本人の希望も大きいですが、就職に有利な学部はどういった分野だと思いますか?ちなみに、文系です
文系で就職に有利な学部、気になりますよね。
一般的には、経済・経営・商学部は企業への就職に強く、法学部は公務員や法務系に有利です。語学や国際系もグローバル企業に人気があります🌏
ただ今は「どの学部か」よりも「大学時代にどんな経験をしたか」が重視される時代です。
実は私も、東大生の就職人気企業で採用担当をしていますが、やはり学部名よりも本人の主体性や行動力を見ています✨
慶應は発達ゆっくりなお子さんは少なめな印象でしょうか?面接や体育もどんな感じか気になります
慶應は自主性を重んじる校風なので、発達がゆっくりなお子さんにはややハードに感じることもあるかもしれませんね💭
面接では受け答えの内容より「その子らしさ」や親子の雰囲気が見られます。体育は運動能力より協調性や意欲重視の傾向です🏃♂️
新6年明日初の合不合判定です。会場も志望校の学校だしとても緊張しています(母親が)
初めての合不合、しかも志望校での受験となると、お母さまが緊張してしまうのも自然なことだと思います。
結果は気になるところですが、今日はお子さんにとって「場慣れ」の大切な一歩。緊張も含めて経験になっていきます。
四科のまとめの効果的な進め方があれば教えてください
四谷大塚の「四科のまとめ」は、6年生の総仕上げに最適な教材ですね。1単元=約1時間を目安に、1日2〜3科目ペースで進めるのがおすすめです。まずは「押さえておきたいポイント」で基礎を確認し、「使いこなしたいポイント」で実践力を養いましょう。親が進行管理を手伝うと、学習の質が上がります。反復がカギです!
小6男子、理科がとても苦手です。いい対策方法ありますか?
理科が苦手でも大丈夫!コツコツ取り組めば必ず力になります💪
① 分野ごとに原因を整理
- 「計算系」か「暗記系」かを見極める
- 計算は「型の暗記」、暗記は「絵や図、実物」でイメージ!
② 苦手単元をピンポイント復習
- 「メモリーチェック」や「四科のまとめ」がおすすめ
- 1日1単元×10分でOK、短く回すのがカギ
③ 解けた体験で“得意化”へ
- 間違えた問題を解き直し→できたらシールや星でご褒美✨
🐻❄️しろくまのひとこと
理科は“きっかけ”で一気に伸びる教科!「わかった!」「できた!」の積み重ねが自信につながります。無理せず、笑顔で乗り越えていきましょう!
小6サピ、早稲アカ生が個別併用し始めました。個別に課金する費用対効果ってどのぐらいありますか?そんなに課金&時間を埋めて親子共々潰れないか心配です
個別併用、周りが始めると焦りますよね。でも費用対効果は「目的しだい」だと思います。苦手克服や志望校対策に的を絞れば効果大ですが、なんとなく不安で詰めると親子で疲弊します💦
時間と気力に余白を残しつつ、ピンポイント活用がおすすめです。
ACの教育虐待CMが頭から離れません。どうしたらポジティブ中学受験を進めていけますか?
「あなたのためだから」という言葉は、親の理想の押しつけに感じます。実際、それが本当に子どもにとって最善かは誰にもわかりませんし、親だって完璧ではありません。 だからこそ大切なのは、子どもと一緒に考え、悩み、進んでいく姿勢。正しさは一つじゃなく、対話の中で見つけていくものだと思います。 中学受験をポジティブに進めるためには、「結果」よりも「プロセス」を大切にすること。小さな成長や努力を一緒に喜び合い、子どもの意志を尊重することが何よりのエネルギーになります。
過去問、初めての実施。どのくらいでしたか
中学受験の過去問、初回の得点は2〜5割くらいのご家庭が多いです。特に第一志望校は難度も高く、2〜3割でも「普通のスタート」と考えて大丈夫です。
大切なのは、間違い直しから「どう伸ばすか」を考えること。初回は“慣れる”が目的です。これからの積み重ねが力になりますよ!
中高6年間で課外授業(海外研修など含め)にどのくらい費用はかかりましたか?
学校によって全く違います。長男は課外授業がほぼなかったので、中高6年間で費用はほとんどかかっていません。一方で次男は中学3年間で2回海外研修に行っていることもあり、200万円近くはかかっていると思います。
中学受験のための四則計算の問題集をご存知でしょうか
こちらの記事にまとめています
小6男子、答え合わせを未だに正確にできません。家でも自習室でも進まず…声がけ等ありますか?
答え合わせが苦手な子、けっこう多いんですよね。面倒だったり、ミスを直すのが嫌だったり…。
「丸つけは“終わり”じゃなくて“伸びるチャンス”だよ」と伝えて、直しの価値を一緒に見つけてあげるのが大切です。
タイマーで区切ったり、最初は親と一緒にチェックするのも効果ありです。焦らず習慣にしていきましょう📣
新小5。算数の基礎は身についているよう。あと一歩成績を伸ばすには何をしたら良いでしょうか。
新小5で算数の基礎ができているのはとても良い状態ですね!あと一歩伸ばすには「解法の引き出し」を増やすことと、「なぜそう解くのか」を説明できる練習がおすすめです。
応用問題に少しずつ触れ、解き方の選択肢を広げていきましょう。思考力を育てる時期、大事にしたいですね。
本人はスポーツより勉強が良いと中受塾に通っています。ただ、中受はしないと言ってる息子をどうやって受験させる気にさせられるのかを悩んでおり…アドバイスをもらえると嬉しいです。
塾には行くけど受験はしたくない」…矛盾しているようで、実は本音なのかもしれませんね。
まずは「なぜ受験したくないのか」をじっくり聞いてあげることが第一歩。無理に説得せず、興味がありそうな学校の文化祭や説明会に一緒に行って、“行きたい学校”を見つけるのがおすすめです。
気持ちが動く瞬間を大切に。
ズバリ!2025年度スタートの明大世田谷について、ご意見聞かせてください。
明大世田谷、注目度が高いですね!
新しい校名・共学化・明治大推薦枠と、魅力は多いですが「過渡期の学校」であることは念頭に置いておきたいです。教育理念や新校舎、探究型の学びは現代的ですが、内部進学の条件や校風の変化は今後の推移を見極める必要があります。
伸びしろと不確実さが共存する学校ですね。期待しつつ、冷静な見極めも大切だと思います📣
イースタイルについて知りたいです
E-styleは「都立中・高一貫校を本気で目指す子にはぴったりの環境」だと思います。双方向型の授業で思考力を鍛えられるのは魅力的ですね。
ただ、少人数制でしっかり見てもらえる分、合う・合わないがハッキリ出る印象です。受け身なタイプより、質問や対話が好きなお子さんに向いています。
志望校と学び方がマッチすれば、大きな力になる塾だと思います📣
小6親です。塾の弁当の用意くらいしかしていません。親は何をすべきでしょうか?
お弁当、毎回用意されてるだけでも立派なサポートです!でも「それだけでいいのかな…」と悩む気持ちもよくわかります。
親にできるのは、点数じゃなく“努力”や“姿勢”を認めてあげること。安心できる家庭の空気、会話の中の励まし、それが何よりの力になります。
一緒に見守るだけでも、十分です。
インスタ復活されて嬉しいです!未就学児はどの程度先取りされていましたか?読み書きや計算など
未就学児の先取りとしては、ひらがな・カタカナの読み書き(特に50音)や数字の1〜10の読み書きが目安です。計算は1桁の足し算・引き算を具体物で理解する体験がおすすめ。プリントより、日常の中で「数が増える・減る」を実感することが大切です。
まずは「読めた!」「わかった!」の体験を積み重ねていきましょう。
公文、新小3現在F後半ですが、どこまで進めるべきですか?
新小3でF(小6相当)後半はすごいですね!この先は中学内容(G)に入ってしまうので、無理に先へ進むより「定着」が大切です。
中学受験を視野に入れるなら、Fまでをしっかり理解し、計算の正確性とスピードを安定させるのが効果的。文章題や思考力問題に広げていく準備としてもより良いです。
無理なく、楽しくを大事に!
Wに通塾、元々理科好き息子。5年になり理科が難しいのか量が増えた?で、嫌いと言い出し勉強法は?
5年からの理科、内容も量も増えて“理科好き”でもつまずきやすい時期です。嫌いになりかけたら、図や動画での理解+要点整理で「わかる!」を積み重ねるのがコツです。
また、理科実験教室で「体験から学ぶ楽しさ」を思い出すのもおすすめ。興味を刺激し直すことで、学びが前向きになります。我が家でも小5に理科実験教室似通いましたが、実際に体験することで理科を楽しむようになりました。
好奇心を力に変えていきましょう!
中学受験が終わり、学校の課題ぐらいしかしいません。塾に行かせたいのですが主人が反対しています。留年しないか心配です。立命館附属です。私も受験が終わり仕事がフルタイムになったため構うことができませんが、何とかなりますでしょうか?
受験後の学習ギャップ、心配になりますよね。特に附属校での“油断”は落とし穴に…。補助輪が外れて、自走できるまでが正念場です。
親が見られない状況なら、まずは学習習慣を整えるための個別指導塾がおすすめです。大学受験向けより“学校内容フォロー重視”の塾が合います。
中学で留年スレスレですと、高校で留年する確率はかなり高まりますし、進学先の学部を選ぶこともままなりません。学習習慣をつけることは複利で効いてくるので、早めの対処が、その後の安定に大きくつながります。おすすめの塾を記事で紹介しているので、参考にどうぞ。
おすすめの塾を記事で紹介しているので、参考にどうぞ。
中高一貫校の中だるみ対策に最適な個別指導塾WAYSの口コミ・評判や料金を解説!
小2男子、中学受験をしたいというけど家庭学習はなかなか身が入らない。どうしたらいいですか?
「中学受験したい」と言ってくれるのは嬉しいけど、実際の勉強が続かない…よくあるお悩みです。
この時期はまず「勉強って楽しい!」を感じさせるのが第一歩。短い時間・ゲーム感覚での学習や、できたらたくさん褒めてあげる声かけが効果的です✨
意志より“習慣”がカギ。少しずつ続ける力、育てていきましょう📣
パズル道場に興味があります。天才パズル全巻セットを購入して家庭で親とするのはありですか?
パズル道場は思考力を育てる良い教材で、天才パズルも家庭学習に◎です。ただ、親が常に付き合うのは正直大変かもしれません💦
パズル道場を取り入れている塾も沢山あるので、そう言った塾でパズル道場だけ通うのもありだと思います。
無理なく、楽しんで続けてくださいね!
慶應義塾普通部に入学後に求められる家庭学習や先生の雰囲気や考え方を教えて下さい
慶應普通部では、入学後に「自ら学ぶ姿勢」が強く求められます。家庭学習は授業の復習+定期テスト対策が中心で、塾より学校内容に合った学習が重要です。
先生方は自主性を大切にし、労作展など自分で考える活動も豊富。親が過干渉にならず、見守るスタンスが合う校風です。
“自分で動ける子”にとって、とても伸びる環境だと思います📣
喘息持ちのため、やや欠席多め。慶應中受や進級時に影響ありますか。
喘息で欠席が多めとのこと、ご心配ですよね。慶應の中学受験では小学校の先生に報告書を書いてもらうので、出欠の記録についても報告されます。ただし、欠席日数が直接不利になったということは基本的にないと考えています。合格した子を見ても、だいたいが塾の成績順です。
また、入学後の進級では「定期試験での評価」が重視されるため、欠席が多くても学習フォローができていれば大きな影響は出にくいです。逆に成績が不足していれば中学生でも留年はあります。
健康第一で、無理なく続けてください。
中学受験の家庭教師でおすすめはありますか?
家庭教師が向いているのは、自分のペースでじっくり理解したい子や、塾のフォローが必要な子、一対一の方が集中できるタイプです。
きめ細かく対応してくれる分、相性も大切になりますね。
おすすめの家庭教師サービスは記事にまとめていますので、よければ参考にしてみてください。
小6女子、復習や宿題で寝る時間が遅いです。何時までと決めていましたか?
小6で復習や宿題が多く、つい夜更かしに…悩ましいですよね。しろくま家では22時までには寝るを基本にしていました。ただ、22時から寝る準備して実際に寝るのは23時を過ぎるということも結構ありました💦
塾の宿題が終わらない日は「明日の朝に仕上げよう」と切り替えて、なるべく睡眠優先。寝不足だと効率も下がるので、メリハリが大事です💤
体も心も元気に受験を乗り越えてほしいですね。
インスタグラムでのアンケート結果(299人回答)

小5男子。S60ですが算数苦手で初見問題はお手上げ。テキスト反復以外にすべきことは何でしょうか?
S60でも算数が苦手、特に初見問題に弱い子、意外と多いです。そういう子は多くの場合、「解法の意味」より「手順の記憶」で解いているので、「なぜそう解くか?」を言語化する練習が効果的。考え方を説明することで、パターンの“使い回し”がしやすくなります。
できなかった問題を解説みて自力で解いた後に、親に解説するようにしてみてください。我が家でも、この方法で算数の成績が安定しました。思考の可視化で初見問題にも対応しやすくなりますよ!
慶應で普通部、中等部、SFCで雰囲気の違いシロクマさんの感じる感想をお伺いしたいです
慶應の3校、それぞれに色がありますが、進学とともに外部生が増える中で、だんだんと校風の差は薄れていくのが現実ですね。
それでも、普通部の男子校らしい濃密な人間関係、中等部の共学ならではの空気感、SFCの自由な発想や多様性は、入学時の3年間でしっかり子どもの中に根を下ろしているかなと。
共学はどうしても“陽”の雰囲気が強くなりがちで、文化系の子が目立ちにくい印象もあります。(ただ、中等部生も高校は男子校になりますが)
それぞれの文化祭に行くと学校の雰囲気の違いもよくわかると思います。
新小5、都立一貫志望、N塾2教科Z会通信で都立対策してます。このままの勉強法でいいか悩みます
都立一貫を目指しているのであれば、バランス良く取り組まれてい流と思います。
ただ都立は「思考力・記述力勝負」なので、2教科だけでなく適正検査に向けた作文練習も少しずつ取り入れるとよいかなと。このままでも良いですが、5年後半から「適性型の演習」を意識できると安心です。
新小4の娘。息子の時と違ってスピードも理解力も遅く算数に苦戦しています
きょうだいで違いがあると、どうしても比べてしまいがちですが、成長のペースは本当に人それぞれですよね。
新小4なら、まだまだ「算数の土台づくり」の時期。焦らず、図をかく・具体物で確かめる・声に出すなど、体感をともなう学びがおすすめです。
「できた!」を一つずつ積み重ねていきましょう。

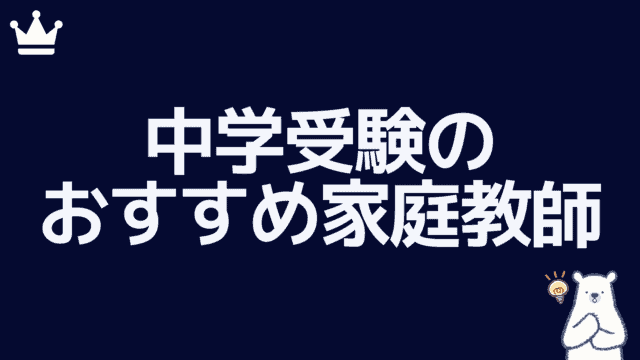
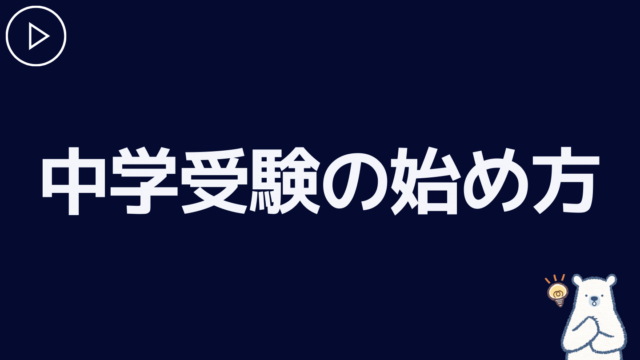
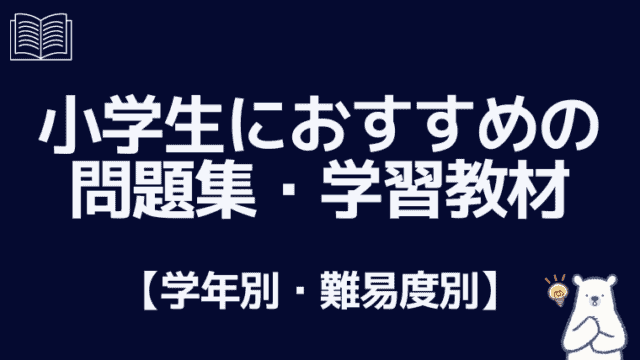
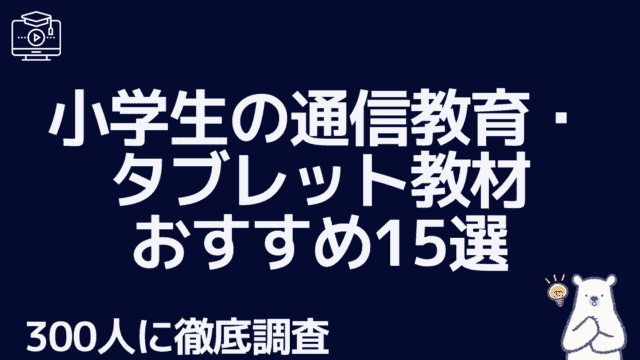

 個別指導SS-1
個別指導SS-1 
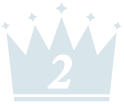 個別教室のトライ
個別教室のトライ 
 国語特化の個別指導ヨミサマ。
国語特化の個別指導ヨミサマ。